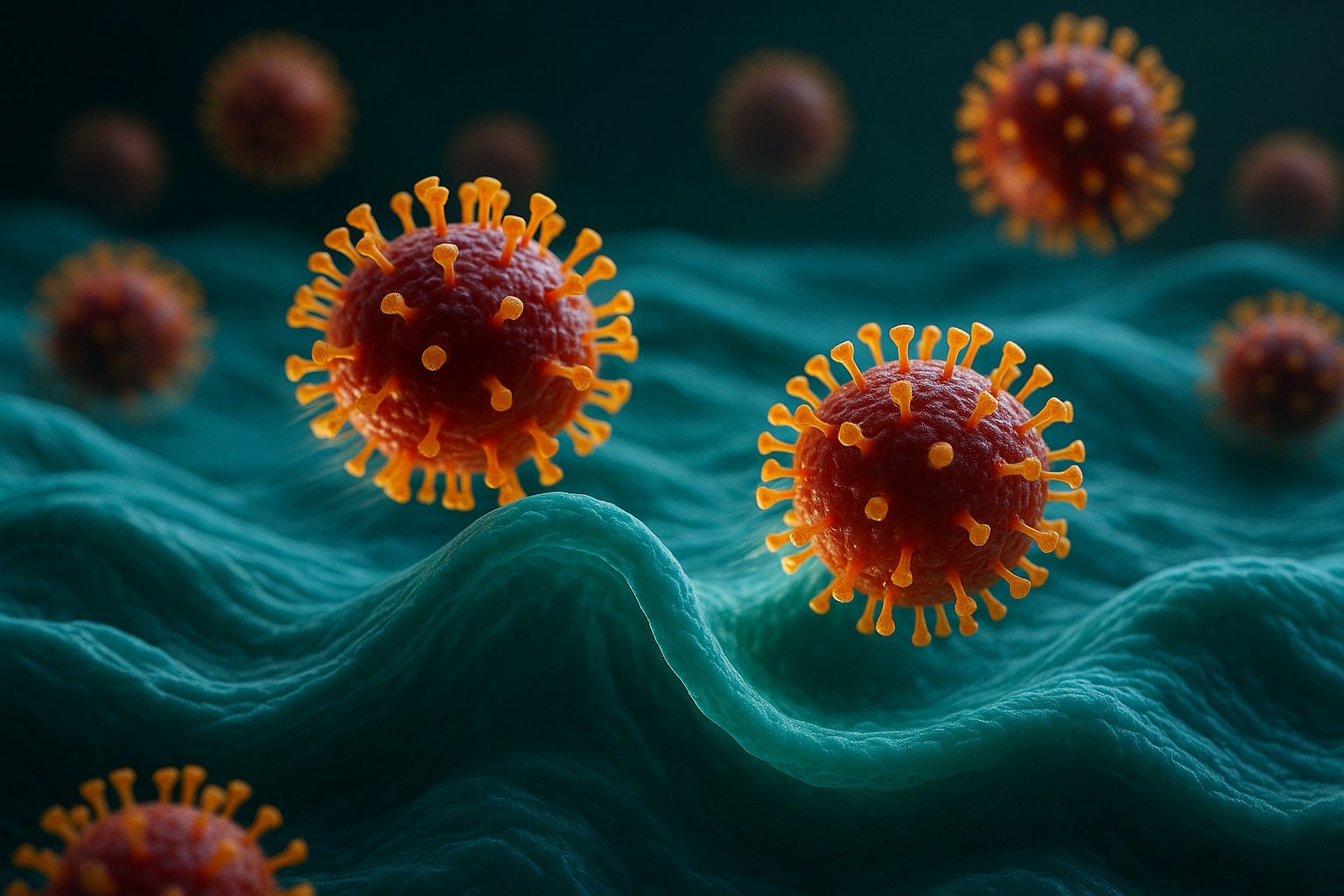ETH Zurich主導の国際チームが日本研究者を含むメンバーで、新しい高解像度イメージング技術を用いて、インフルエンザウイルスがヒト細胞に侵入する様子を生で観察した。この研究は、細胞がウイルスと積極的に関与し、細胞膜に沿ってサーフィンのようなプロセスで内部に引き込むことを示し、標的型抗ウイルス療法の開発に寄与する可能性がある。
インフルエンザウイルスは、発熱、四肢の痛み、鼻水を特徴とする季節性疾患を引き起こし、飛沫を通じて体内に入り、気道の細胞を感染させる、とETH Zurichが報告。
スイスと日本の研究者らが、この感染プロセスを前例のない詳細で調べた。彼らが独自に開発した顕微鏡技術により、ペトリ皿で培養されたヒト細胞の表面をズームインし、個別のインフルエンザAウイルスが生きた細胞に侵入する様子を、高解像度でリアルタイム観察できる。
ETH Zurichの分子医学教授、Yohei Yamauchi氏が主導した研究では、細胞は受動的な犠牲者ではないことが判明した。むしろ、ウイルスの取り込みに積極的に寄与する。「我々の体細胞の感染は、ウイルスと細胞のダンスのようなものだ」とYamauchi氏は述べた。
細胞は感染から何の利益も得ないが、ウイルスは細胞がホルモン、コレステロール、鉄などの必須物質を輸入するために頼る日常的な取り込みシステムを乗っ取る。
感染を開始するため、インフルエンザウイルスは細胞表面の特定の分子に結合する。ETH Zurichによると、ウイルスはその後膜上を効果的に「サーフィン」し、次々と分子に付着して表面をスキャンし、多くの受容体分子が集まる侵入部位に到達すると効率的な取り込みが可能になる。
細胞の受容体が膜にウイルスが付着したことを検知すると、細胞はその粒子を包み込むように動き始める。その場所に小さなくぼみ、またはポケットが生じ、構造タンパク質クラトリンによって形成・安定化される。ポケットが深くなるにつれウイルスを包み込み、ベシクルとして芽出し分離する。細胞はこのベシクルを内部に運び、そこでベシクルの外膜が溶解してウイルスを放出する。
新しい技術を用いて、研究者らはこのプロセスの複数の段階で細胞がウイルスを助けることを示した。ウイルスが結合した部位にクラトリンタンパク質を積極的に募集し、細胞表面が上向きに膨らんで粒子を捕捉するのを助ける。これらの波状の膜運動は、ウイルスが表面から離れ始めると激しくなる。
これまで、インフルエンザ侵入の主要側面は電子顕微鏡で主に研究されてきたが、これは細胞を固定・破壊する必要があり静的スナップショットしか得られず、または蛍光顕微鏡では空間分解能が低く、ナノスケール表面ダイナミクスへの洞察が限定的だった。
新しい手法virus‑view dual confocal and AFM(ViViD‑AFM)は、原子間力顕微鏡と蛍光顕微鏡を組み合わせ、ウイルス侵入の微細スケールダイナミクスをリアルタイムで追跡する。この方法は、Enhanced visualization of influenza A virus entry into living cells using virus‑view atomic force microscopyと題された論文で詳細に記述され、2025年9月にProceedings of the National Academy of Sciencesに掲載された。
ViViD‑AFMにより科学者らが感染をその場で観察可能であるため、ETH Zurichチームは現実的な条件下で細胞培養で抗ウイルス薬候補を直接テストする強力な手段を提供すると述べている。研究者らはまた、この技術を他のウイルスやワクチン研究に適用可能で、多様な粒子が細胞と相互作用し取り込まれる様子をリアルタイムで観察できると指摘している。